行水(ゆくみず)にも淵瀬(ふちせ)あり 人の世に窮達(きゅうたつ)なからめやは
(水の流れに淵(穏やかな場所)や瀬(流れの急な場所)があるように、人生にも良いときも悪いときもある)
樋口一葉(ひぐち いちよう)
これは五千円札の肖像画で知られる樋口一葉(ひぐち いちよう)の言葉です。
明治初期の、まだ女性の社会進出が果たされていない時代。ましてや小説家という職業は、男性であっても道楽者だと思われていた時代。そんな時代に小説を書き、その原稿料で生活していくと志した樋口一葉。
樋口一葉といえば『たけくらべ』や『にごりえ』などを書いた女性作家、という程度しか世に知られていないのではないでしょうか。
樋口一葉って一体どんな人物だったのでしょう?
樋口一葉ってどんな人?

樋口一葉の父は、江戸幕府から明治新政府に変わる激動の時代に、うまく新政府の下僚に職を得、貧しいながらも東京府士族でした。
明治5年に生まれた一葉は早熟のとても頭のいい子で、小学校の先生からも目をかけられるほどだったそうです。
しかし「女子には学問を長くさせてはいけない。針仕事と家事見習いをさせねば」という母親の教育観から、12歳の頃に小学校をやめることになります。
勉強好きだった一葉は、学校をやめされられたことが死ぬほど悔しかったようで、父の情けで一葉が14歳のとき、歌塾『萩の舎(はぎのや)』に入塾。
『萩の舎』には同じ年頃の上流階級の娘さんも多く通っていましたが、貧しいながらも賢い頭脳と才能ある一葉は何かと目をかけてもらっていたといいます。
入塾して三年ほど経ったころ、父親と長兄が相次いで亡くなります。次兄は分籍しており、姉は結婚して家を出ていたため、まだ20歳にも満たない一葉が樋口家の相続戸主となったのです。
この時代の民法では、自分だけでなく母や妹の面倒も戸主である一葉がみなくてはいけません。
一葉の最終学歴は小学高等科のため、いくら才があっても教職にはつけず、針仕事だけでは母親と妹を養うことができない。
当時は活版印刷が世に出始め、出版界が成立しかけていたこともあり、読書好きで勉強熱心な一葉は小説を書いて生活していくことを決心します。
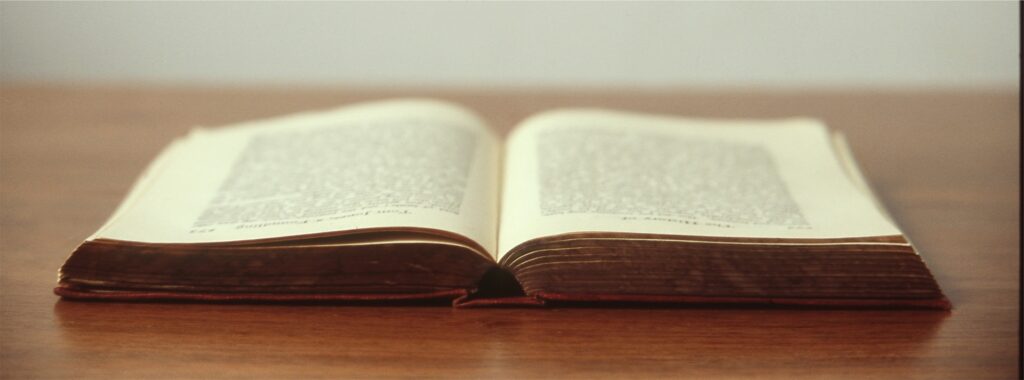
小説は、半井桃水(なからい とうすい)という小説家に教わりました。
しかし家計が苦しくて思うように執筆もはかどらず、周りの人に借金をしたり、慣れない商売をはじめてみたりと、生活は相当に厳しいものでした。芸者や遊女などに身を落とさなかったのが不思議なくらいだといいます。
一葉は極貧のなかでもユーモアを忘れず、小説家らしい鋭いまなざしで世の中を見、すべて作品の糧にしていました。
そして萩の舎からの知り合いのツテを頼りに、一葉はすこしづつ小説を発表します。
作品の転機となったのは「文学界」で発表した『大つごもり』。それからの一年弱は【奇跡の14ヶ月】といわれており、一葉の代表作となる作品が次々と発表され、評判を呼びます。
1986年には「文芸倶楽部」に『たけくらべ』が再掲され、幸田露伴や森鴎外といった当時の文豪たちが一葉を絶賛。しかしその年の11月、当時は治療法がなかったという肺結核で、若干24歳で一葉はこの世を去ります。
駆け出しの頃に亡くなってしまった一葉が小説家として名を残したのは、一葉の死後、妹が一葉の遺品や作品・日記などを大切に守り、世に出すことに尽力した結果でもあります。
まとめとして

行水にも淵瀬あり 人の世に窮達なからめやは
(水の流れに淵や瀬があるように、人生にも良いときも悪いときもある)
樋口一葉
一葉の前にも女性作家はいましたが、その多くは中・上層階級で父や夫という後ろ盾のある女性たちばかりで、それも趣味に近いものばかりでした。
後ろ盾がある彼女たちが羨ましいと思ったかもしれません。それでも人一倍強い向上心と大胆さで、不可能と思われた小説家として名を残した樋口一葉。
自分の境遇や時代に負けず、自ら信じた道を生ききった姿に、五千円札の顔に選ばれたのもうなずけますね。
生きていれば誰だって良いときも悪いときもあるのだから、人と比べて自分を卑下したりせず、一葉を見習って自分の人生を生き抜きたいですね。










